AIエージェントという言葉を耳にする機会が急速に増え、監査や会計の世界でもその存在感は無視できないものになっています。かつては人の手で行われていた膨大な監査手続が、いまや自律的に判断し行動するAIによって置き換えられつつあります。
こうした変化は単なる効率化にとどまらず、監査の質やスピード、さらには「信頼」の定義そのものを変え始めています。監査法人と企業の関係も、人と人のやり取りから、エージェント同士が連携する新しい協業モデルへと進化しています。
本記事では、AIやエージェント技術に関心の高い方や専門家の方に向けて、なぜ今監査領域でAIエージェントが注目されているのか、Big4各社はどのような戦略を描いているのか、そして企業側にはどのような備えが求められるのかを整理します。最新事例やデータを踏まえながら、これからの監査とAIの関係を体系的に理解できる内容をお届けします。
監査とAIが交差する背景と時代の変化
監査とAIが交差する背景には、ここ数年で加速した技術進化と社会要請の同時進行があります。2023年以降、生成AIが一気に普及したことで、監査現場でもデータ処理や文書理解の自動化が現実のものとなりました。しかし2025年を境に、潮目はさらに変わります。単なる自動化ではなく、AIが自律的に判断し行動する「エージェント化」が本格化したことで、監査の前提条件そのものが揺さぶられ始めました。
デロイトのTech Trends 2026によれば、企業内で稼働するAIは「シリコンベースの労働力」として再定義されつつあります。これはRPAの延長線ではなく、知覚・推論・行動を循環させる存在として、人間の業務プロセスに組み込まれることを意味します。監査においては、証憑突合や異常値検知といった従来ジュニアスタッフが担ってきた作業が、24時間稼働するAIエージェントに置き換わりつつあります。
この変化は効率化にとどまりません。監査の「質・スピード・信頼」の定義が同時に再構築されている点が重要です。AIが全取引データを横断的に検証できるようになったことで、サンプリング前提の監査モデルは見直しを迫られています。PwCやKPMGが示すように、全数分析と継続的監査はすでに理論ではなく実装段階に入っています。
| 従来の監査 | AIエージェント時代の監査 |
|---|---|
| 人手中心・期末集中 | 自律エージェント・継続的 |
| サンプリング前提 | 全数データ分析 |
| 事後的な検証 | リアルタイムに近い保証 |
背景には、規制当局や投資家からのプレッシャーもあります。財務情報の信頼性だけでなく、プロセスの透明性や説明可能性が強く求められる中、AIを使わない監査はリスクになりつつあります。日本公認会計士協会や金融庁がAI活用を前提とした議論を進めていることも、この流れを裏付けています。
重要なのは、AI導入が監査人の価値を下げるのではなく、むしろ人間の判断力と倫理的意思決定を際立たせる環境を生み出している点です。AIが前処理と分析を担うことで、監査人は「何を疑うべきか」「どこにリスクの本質があるのか」という高度な判断に集中できます。監査とAIの交差は、不可逆的な時代の変化として、すでに現実のものとなっています。
自動化から自律化へ進化するAIエージェント
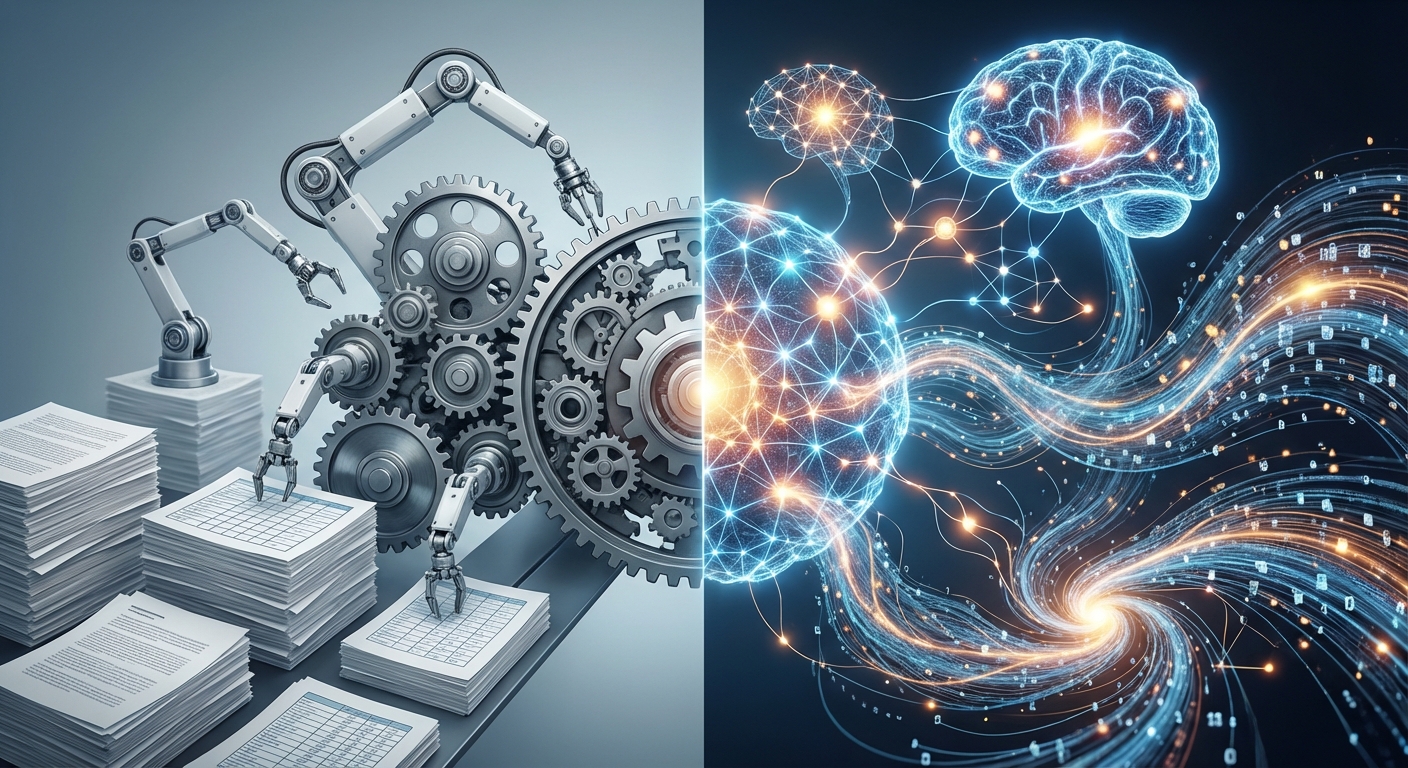
企業システムにおけるAI活用は、長らく自動化という枠組みで語られてきました。RPAや従来型の機械学習は、あらかじめ定義されたルールやフローを高速に実行する点で価値を発揮してきましたが、その本質は人間の指示に従うツールに留まっていました。2026年現在、この前提は大きく覆されています。生成AIの進化とエージェント技術の成熟により、AIは自ら目標を理解し、計画し、行動を修正する存在へと進化しています。
この変化の核心は、AIが単なる処理装置ではなく、判断主体として振る舞い始めた点にあります。Anthropicなどが定義するAgentic AIは、知覚・推論・行動という認知サイクルを自律的に回します。これは「人がAIを操作する」構図から、「AIが人と協働する」構図への転換を意味します。**自律化とは、処理速度の向上ではなく、意思決定プロセスそのものの再設計**だといえます。
監査や会計の領域では、この違いが特に顕著です。従来の自動化は、証憑突合やデータ整形といった定型業務の効率化が中心でした。一方、自律型エージェントは、必要なデータを自ら取得し、不整合の背景を推論し、次に取るべき行動を選択します。デロイトのTech Trends 2026が示す「シリコンベースの労働力」という概念は、こうしたAIをデジタルな同僚として位置づけています。
| 観点 | 自動化AI | 自律型AIエージェント |
|---|---|---|
| 役割 | 定義済みタスクの実行 | 目標達成のための行動選択 |
| 判断 | ルールベース | 推論とフィードバック |
| 人との関係 | ツール | 協働パートナー |
この自律性を現実の業務に接続したのが、Model Context Protocolの標準化とSmall Language Modelsの実用化です。MCPにより、エージェントはERPや文書管理システムと安全に接続できるようになりました。また、KPMGジャパンが取り組むようなタスク特化型SLMは、巨大モデルよりも高い精度と説明可能性を実現しています。**自律化は万能化ではなく、専門化によって成立している**点が重要です。
さらに2026年の特徴として、単体ではなく複数のエージェントが連携するオーケストレーションが挙げられます。会計基準解釈、データ分析、リスク評価といった役割を持つエージェントが相互に検証し合う構造は、人間の専門家チームに近い振る舞いを見せます。これは監査品質の向上だけでなく、判断過程の透明性にも寄与します。
自動化から自律化への進化は、効率化の延長線では語れません。**AIが判断する時代において、人間の価値は判断を下すことから、その判断を設計・監督することへ移行しています**。この役割転換を理解できるかどうかが、AIエージェント時代の競争力を左右する分水嶺となっています。
監査を支える技術基盤:MCPとSLMの役割
監査を支える技術基盤として、2026年時点で特に重要性を増しているのがMCPとSLMです。この二つは、AIエージェントを単なる分析ツールから「監査プロセスを自律的に実行できる存在」へ引き上げるための土台として機能しています。
まずMCPは、LLMやエージェントが外部システムと安全かつ標準的に接続するための共通プロトコルです。従来、ERPや会計システムとの連携は個別開発が必要で、監査ごとに仕様調整やセキュリティ審査が発生していました。MCPの普及により、監査エージェントは「どのデータに、どの操作権限で、どの目的でアクセスするか」を明示した形でツールを呼び出せるようになり、監査証拠の取得プロセスそのものが再現可能かつ説明可能になっています。
Anthropicなどが提唱する設計思想では、MCPは単なる接続規格ではなく、エージェントの行動範囲を制御するガバナンス層と位置づけられています。監査文脈では、請求書データの抽出、銀行明細との突合、差異発生時の問い合わせといった一連の操作を、ログ付きで連鎖的に実行できる点が評価されています。
| 観点 | MCP導入前 | MCP導入後 |
|---|---|---|
| システム連携 | 個別API開発 | 標準化されたツール接続 |
| 監査証跡 | 人手中心で断片的 | 操作ログが自動生成 |
| セキュリティ管理 | 案件ごとに設計 | 権限制御を一元化 |
一方、SLMは監査品質を左右するもう一つの中核技術です。Big4各社やIBMの議論でも共通しているのは、監査や税務のような高機密・高専門領域では、巨大な汎用LLMよりもタスク特化型のSLMが適しているという認識です。KPMGジャパンが進める社内専用SLMの取り組みでは、日本の会計基準や業界慣行を集中的に学習させることで、誤解釈や過剰生成のリスクを抑えています。
SLMの強みは、精度と統制の両立にあります。モデルサイズが小さいためオンプレミスやプライベートクラウドで運用しやすく、個人情報保護法や監査基準への対応もしやすい構成です。IBMが指摘するように、説明可能性やトレーサビリティを確保しやすい点は、監査証拠としてAI出力を利用するうえで決定的な差になります。
最終的に重要なのは、MCPが「行動の安全な通路」を提供し、SLMが「判断の精度と一貫性」を担保するという役割分担です。この二層構造によって、AIエージェントは人間監査人の補助ではなく、監査プロセスの一部として組み込まれる存在へと進化しています。監査の信頼性は、もはや人だけでなく、この技術基盤の設計思想そのものに支えられていると言えます。
Big4監査法人におけるAIエージェント戦略の全体像

Big4監査法人におけるAIエージェント戦略の全体像は、単なる業務効率化を超え、監査という専門サービスの提供モデルそのものを再設計する試みにあります。2026年時点で共通して見られるのは、生成AIを補助的に使う段階から脱し、**自律的に行動し判断を支援するAIエージェントを監査基盤の中核に据える**という明確な意思です。
この戦略転換の背景には、全社的なプラットフォーム投資があります。Big4はいずれも、監査ツールを点在するアプリケーションの集合体としてではなく、エージェントが横断的に動作する統合基盤として再構築しています。デロイトのTech Trends 2026が指摘するように、AIエージェントは「シリコンベースの労働力」として、人間の監査人と同じワークフロー空間で役割分担される存在として位置づけられています。
戦略の違いはあるものの、各社の方向性を整理すると、重視している軸が見えてきます。
| 戦略軸 | 主な狙い | 監査価値への影響 |
|---|---|---|
| プラットフォーム統合 | AIエージェントを監査基盤に標準搭載 | 属人性の低下と品質の均質化 |
| 自律化レベルの引き上げ | 判断・実行を伴うタスク委譲 | 監査スピードと網羅性の向上 |
| ガバナンス重視 | 説明可能性と監督性の確保 | 監査意見の信頼性維持 |
特に重要なのは、**AIエージェントを前提とした監査プロセス設計が、グローバルレベルで標準化されつつある**点です。KPMGやPwCの公開情報によれば、エージェントの行動ログや推論過程を監査証拠として扱う設計が進み、人間の監査人は結果を再検証し、最終判断を下す役割にシフトしています。これは国際監査基準の「専門的懐疑心」を、AI時代に再解釈した動きとも言えます。
また、Big4各社は競争しながらも、共通してオープンアーキテクチャを採用しています。MCPのような標準化技術を前提に、外部ツールやスタートアップ技術を組み込める構造を維持することで、技術進化のスピードに追随できる柔軟性を確保しています。これは、単一ベンダー依存による技術的ロックインを避けるための、極めて戦略的な判断です。
この全体像から見えてくるのは、AIエージェントが監査人の代替ではなく、監査品質を拡張するインフラとして扱われている現実です。各社とも、最終責任は人間が負うという原則を堅持しつつ、**判断に至るまでの探索・分析・検証をエージェントに委ねる**という役割分担を明確にしています。Big4の戦略は、監査の未来像を実装レベルで先行提示していると言えるでしょう。
EYに見る文書解析と不正検知の高度化
EYにおける文書解析と不正検知の高度化は、監査実務の中でも特に人手依存が強かった領域を根本から変えつつあります。2026年1月に本格稼働したDocument Intelligence Platformは、単なるOCRや自動仕訳支援を超え、証憑そのものの信頼性を評価する中核基盤として位置付けられています。
このプラットフォームの特徴は、生成AIによる文脈理解と画像解析AIを組み合わせた多層的な検証にあります。請求書や契約書を読み取る際、金額や日付を抽出するだけでなく、取引条件や契約期間と会計データの整合性まで自動で照合します。さらに人間の目では判別が難しい改ざん痕跡をピクセル単位で検知する点が、従来手法との決定的な違いです。
具体的には、承認印のコピー貼り付け、不自然な文字の再描画、メタデータ上の作成日時と内容の齟齬といった兆候を検出し、リスクスコアとして監査チームに提示します。情報処理学会や画像フォレンジック分野の研究でも、微細な画素分布の不整合が改ざん検知に有効とされており、EYはこうした学術的知見を実装レベルに落とし込んでいます。
| 観点 | 従来の文書レビュー | DIP導入後 |
|---|---|---|
| 確認対象 | 金額・日付中心 | 文脈・契約条件・画像特徴 |
| 不正検知 | 目視・経験依存 | 画像解析とAI推論 |
| 対象範囲 | サンプル抽出 | 全証憑を網羅的に分析 |
この仕組みはすでにEY新日本が担当する3,805社に展開されており、実運用規模の大きさも特筆点です。ZDNet Japanなどの報道によれば、パイロット段階で確認されたのは、ヒューマンエラーの減少だけでなく、監査人が不正リスクの背景分析や経営判断の妥当性評価により多くの時間を割けるようになったという点でした。
重要なのは、AIが不正を断定するのではなく、疑義の優先順位付けを行う補助線として機能していることです。これにより監査判断の最終責任は人間に残しつつ、見逃しリスクを構造的に低減できます。EYのアプローチは、監査品質を速度と網羅性の両面から引き上げる現実解として、他分野のコンプライアンスやリスク管理にも示唆を与えています。
KPMGとDeloitteが描くマルチエージェントの未来
**KPMGとDeloitteは、マルチエージェントを単なる業務効率化の延長ではなく、組織と専門知の構造そのものを再設計する存在として位置付けています。**両社に共通するのは、単体で高性能なAIを追求するのではなく、役割分担された複数のエージェントが協調し、判断の質とスピードを同時に高める未来像です。
KPMGが描く未来は「オーケストレーションされたエコシステム」に集約されます。KPMG Claraを中核に、会計基準解釈、リスク評価、データ取得といった専門エージェントが常時連携し、監査人の意思決定を多面的に支援します。KPMGの調査によれば、AIエージェントはすでに企業戦略のバックボーンとして認識されており、特に不況下でも継続投資される領域だと報告されています。
この構想の本質は、**人間の判断を代替するのではなく、判断が行われる前段階を高度に構造化する点**にあります。エージェント同士が仮説を立て、検証し、相互に異論を提示することで、監査人は最終判断に集中できます。KPMG自身が「人間の専門家チームをデジタル上で再現する試み」と表現するように、集合知の再現が狙いです。
| 観点 | KPMGの方向性 | Deloitteの方向性 |
|---|---|---|
| 基本思想 | 全体最適を志向するエコシステム | 機能特化型エージェントの積み上げ |
| 中核プラットフォーム | KPMG Clara | Omnia |
| 価値の源泉 | エージェント間の協調と相互検証 | ドメイン知識に特化した深い専門性 |
一方、Deloitteが強調するのは「専門化されたマルチエージェント」の現実的展開です。Zora AIに代表されるように、財務や調達など特定領域に深く最適化されたエージェントを複数配置し、人間の監督下で連鎖的にタスクを遂行させます。DeloitteのTech Trends 2026では、こうしたエージェント群を「シリコンベースの労働力」と定義しています。
注目すべきは、Deloitteが同時に「エージェントの現実とのギャップ」を明確に指摘している点です。レガシーシステムや未整備なデータ基盤が、マルチエージェント導入の40%以上を失敗に導く可能性があると警告しています。**理想論ではなく、制約条件を前提に設計する姿勢**が、Deloitteの未来像を特徴づけています。
両社のビジョンは対照的に見えますが、共通しているのは「単独で賢いAIは価値を生まない」という認識です。価値を生むのは、エージェント同士が対話し、矛盾を検出し、人間が納得できる判断材料を提示する構造です。**マルチエージェントは、AIの性能競争から、意思決定アーキテクチャの競争へと舞台を移しつつあります。**
PwCが重視するAIガバナンスと信頼の設計
PwCがAIエージェント時代の監査で最も重視しているのは、技術的な高度化そのものではなく、AIが生み出す判断やアウトプットをいかに「信頼できるものとして設計するか」という点です。PwCはこの課題に対し、AIを単体ツールとして導入するのではなく、ガバナンスを内包した運用基盤として捉え、「PwC AgentOS」を中核に据えた設計思想を明確に打ち出しています。
その象徴が、データ監査ツールHaloと監査ERPであるAuraを軸にしたAIエージェントの統合です。2025年以降、PwCの監査では全数取引データの分析が標準となり、AIエージェントが異常値を検知するだけでなく、なぜそれがリスクと判断されたのかという文脈情報までを構造化して提示する仕組みが実装されています。これは監査人の判断を代替するものではなく、判断の前提条件を透明化するための設計だと位置付けられています。
PwCが掲げるResponsible AIの考え方では、説明可能性と監督可能性が最優先事項です。PwCのグローバル調査によれば、AI活用において明確なガバナンス枠組みを構築している企業は、そうでない企業と比べてステークホルダーからの信頼度が有意に高く、結果として企業価値評価にも正の影響が見られると報告されています。PwCはこれを「信頼のハロー効果」と呼び、AI投資の経済的リターンとして定量化しています。
この思想を具体的なサービスに落とし込んだのが、AI Assuranceと呼ばれるAI保証サービスです。これはAIモデルやエージェントが、どのデータを参照し、どのような統制下で学習・推論・行動しているのかを第三者として検証するもので、従来のIT統制監査をAIシステムそのものに拡張した位置付けです。PwCの発表では、金融・インフラ・ヘルスケアといった高規制業界を中心に導入が進んでいます。
| 設計観点 | PwCの具体的対応 |
|---|---|
| 説明可能性 | AIエージェントの判断根拠をログとして保存し、監査証拠として再現可能に設計 |
| 統制と監督 | Human-in-the-Loopを前提とした権限設計と例外時の自動エスカレーション |
| 独立した保証 | AI AssuranceによりAI自体の信頼性を第三者的に検証 |
さらに注目すべきは、PwCオーストラリアなどで進むAIネイティブな監査プラットフォームの実証です。ここではアジャイル開発を前提に、AIエージェントの挙動を継続的にテストし、ガバナンス設計自体を進化させています。固定的なルールでAIを縛るのではなく、変化を前提に信頼を維持するという発想は、Agentic AI時代ならではの特徴だと言えます。
PwCの取り組みは、AIエージェントが高度化するほどガバナンスは後付けでは成立しないことを示しています。信頼の設計を技術・プロセス・保証サービスまで一貫させる戦略こそが、PwCがAI時代の監査において差別化を図る最大の要因となっています。
監査プロセスはどう変わるのか:APIと継続的監査
APIとAIエージェントの普及は、監査プロセスを「定期的な点検」から「常時稼働する仕組み」へと進化させています。従来の監査は、期末や四半期末にデータを集めて検証する事後的な性格が強いものでした。しかし2026年現在、ERPや会計システムと監査プラットフォームがAPIで直接接続されることで、取引データはリアルタイムに近い形で監査側へ共有されます。
この変化の本質は、データ提出の自動化ではなく、監査の時間軸そのものが再定義された点にあります。デロイトやPwCが示すように、全取引データを対象とした分析が標準化され、サンプリングに依存しない監査が現実のものとなっています。MindBridgeとVEONの事例では、AIが全トランザクションを常時分析し、異常兆候を早期に検知することで、監査の精度と網羅性が同時に高まりました。
APIベースの接続は、企業と監査法人の役割分担にも影響を与えます。監査エージェントは必要なデータを自律的に取得し、企業側の担当者は「資料を渡す人」から「検知された論点を説明・判断する人」へと役割が移ります。KPMGの調査によれば、このモデルではQ&Aの往復回数が大幅に減少し、監査対応工数が構造的に削減されると報告されています。
| 観点 | 従来型監査 | APIと継続的監査 |
|---|---|---|
| データ取得 | 手動提出 | APIによる自動連携 |
| 分析範囲 | サンプル中心 | 全数データ |
| 実施頻度 | 期末・四半期 | 日次・常時 |
こうした継続的監査は、不正や誤謬の早期是正だけでなく、経営への示唆提供という新たな価値も生みます。PwCが指摘するように、リアルタイム監査データは内部統制の改善や資金管理の高度化に直結し、監査が単なるチェック機能から経営インフラの一部へと組み込まれつつあります。
APIと継続的監査の組み合わせは、監査を「終わらせる作業」ではなく「回り続けるプロセス」に変えました。この構造転換こそが、AIエージェント時代における監査プロセス変革の核心だと言えるでしょう。
企業に求められる監査対応エージェントとガバナンス
企業においてAIエージェントの活用が進むにつれ、監査対応は「資料を出す行為」から「エージェントそのものを説明し、統制する能力」へと質的に変化しています。2026年時点では、監査法人が高度な自律型エージェントを用いる前提に立ち、企業側にも同等レベルの準備が求められています。もはや監査対応は経理部門だけの課題ではなく、全社的なAIガバナンスの成熟度を測る試金石となっています。
とりわけ重要なのが「監査対応エージェント」という考え方です。これは監査法人からのデータ要求や質問に人手で対応するのではなく、企業内の会計・業務データ、内部統制文書、意思決定ログを横断的に参照し、整合性のある形で提示する専用エージェントを指します。KPMGジャパンが提唱するように、SLMを用いた自社特化型エージェントは、日本固有の会計慣行や業務フローを反映でき、監査効率と精度を同時に高める手段として注目されています。
監査で真に問われるのは、エージェントが出した「答え」そのものよりも、その背後にある判断プロセスです。デロイトのAIインスティテュート責任者が指摘する通り、ガバナンスのないエージェントの増殖は、意思決定の監査可能性を著しく損ないます。そのため企業には、エージェントの行動を説明可能な形で記録し、後追い検証できる設計が不可欠です。IBMが示すような、複数エージェントにまたがるログと証跡を統合管理する仕組みは、すでに先進企業では標準になりつつあります。
| ガバナンス観点 | 監査での着眼点 | 企業側の具体対応 |
|---|---|---|
| 説明可能性 | 判断理由が人間に理解できるか | 推論根拠・参照データを自動記録 |
| トレーサビリティ | データの出所と加工履歴 | データリネージの可視化 |
| アクセス制御 | 過剰権限や情報漏洩リスク | 最小権限設計と人間の監督 |
PwCのResponsible AIに関する調査が示すように、こうしたガバナンス投資は単なるリスク低減にとどまりません。AIの透明性と統制が担保されている企業は、監査人からの信頼が高まり、結果として監査プロセスの簡素化や追加手続の削減につながる傾向があります。ガバナンスはコストではなく、監査対応力という無形資産として機能し始めているのです。
さらに見逃せないのが、日本企業特有のレガシー環境との関係です。API連携が前提の監査エージェントに対し、バッチ処理中心の基幹システムでは、データ鮮度や一貫性の説明が困難になります。このギャップを放置すると、エージェントの判断が正しくても監査証拠として十分と認められないリスクが生じます。監査対応エージェントの整備は、結果的にデータ基盤の近代化を促す触媒ともなります。
最終的に監査法人が評価するのは、「この企業はAIに判断を委ねても統制が効いているか」という一点です。エージェントが自律的に動く時代だからこそ、人間による設計思想と統治構造が強く問われます。監査対応エージェントとガバナンスの成熟度は、企業のAI経営力そのものを映す鏡であり、2026年以降、その差はより明確に可視化されていくでしょう。
日本市場特有の法規制とスタートアップの可能性
日本市場におけるAIエージェント活用は、独自の法規制環境と密接に結びついています。特に個人情報保護法(APPI)と著作権法は、監査や会計領域でAIを実装する際の設計思想そのものに影響を与えています。**この規制の厳しさは一見すると制約に見えますが、実際には日本発スタートアップにとって差別化の源泉になりつつあります。**
APPIでは、個人データの利用目的の特定、安全管理措置、第三者提供の制限が厳格に求められます。金融庁や日本公認会計士協会の議論でも、クラウド型汎用LLMへの無制限なデータ送信には慎重な姿勢が示されています。これを背景に、KPMGジャパンなどが推進するオンプレミスやプライベートクラウドで稼働するSLM型エージェントが注目されています。**データを国内に閉じたまま高度な自律化を実現する設計は、日本市場特有の最適解です。**
また著作権法を巡っては、生成AIの学習データの適法性が社会的論点となっています。森・濱田松本法律事務所やアンダーソン・毛利・友常法律事務所の解説によれば、企業はAIモデルの学習元や参照データについてデューデリジェンスを行う責任を負います。監査領域では、AIエージェントが参照する契約書や文書データの権利関係を可視化する機能が不可欠となり、この点がプロダクト要件として明確化しています。
| 法規制要素 | 主な制約 | スタートアップの機会 |
|---|---|---|
| 個人情報保護法 | データ国外移転・再利用の制限 | 国内完結型AI、SLM基盤の需要拡大 |
| 著作権法 | 学習・生成物の権利不透明性 | 学習データ管理・証跡化ツール |
| 監査基準・ガイドライン | 説明可能性・監査可能性の要求 | Explainable AI、ログ管理技術 |
このような環境下で、日本のスタートアップは「規制対応力」を競争優位に変えています。LegalOn Technologiesの契約解析AIは、条文単位での根拠提示を重視した設計により、監査証拠としての利用可能性を高めています。Forbes Japanでも指摘されている通り、日本のAIスタートアップは汎用性よりも業務特化と信頼性を重視する傾向が強く、これは監査・会計分野との親和性が高い特徴です。
結果として、日本特有の法規制はAIエージェント導入のブレーキではなく、**高信頼・高付加価値市場を形成するフィルター**として機能しています。このフィルターを前提に設計されたプロダクトこそが、国内のみならず規制強化が進む欧州市場などへの展開可能性を秘めており、日本発スタートアップにとって大きな成長余地を生み出しています。
参考文献
- KPMG:AI at Scale: How 2025 Set the Stage for Agent-Driven Enterprise
- Deloitte:Unleashing agentic AI’s true potential: Strategic approaches for a silicon-based workforce
- ITmedia エンタープライズ:EY新日本、生成AI活用の書類解析システムが本稼働、顧客3805社に展開
- KPMG:KPMG advances AI integration in KPMG Clara smart audit platform
- PwC:Quantifying the value of Responsible AI
- IBM:Building trustworthy AI agents for compliance: The challenge of auditability and explainability
