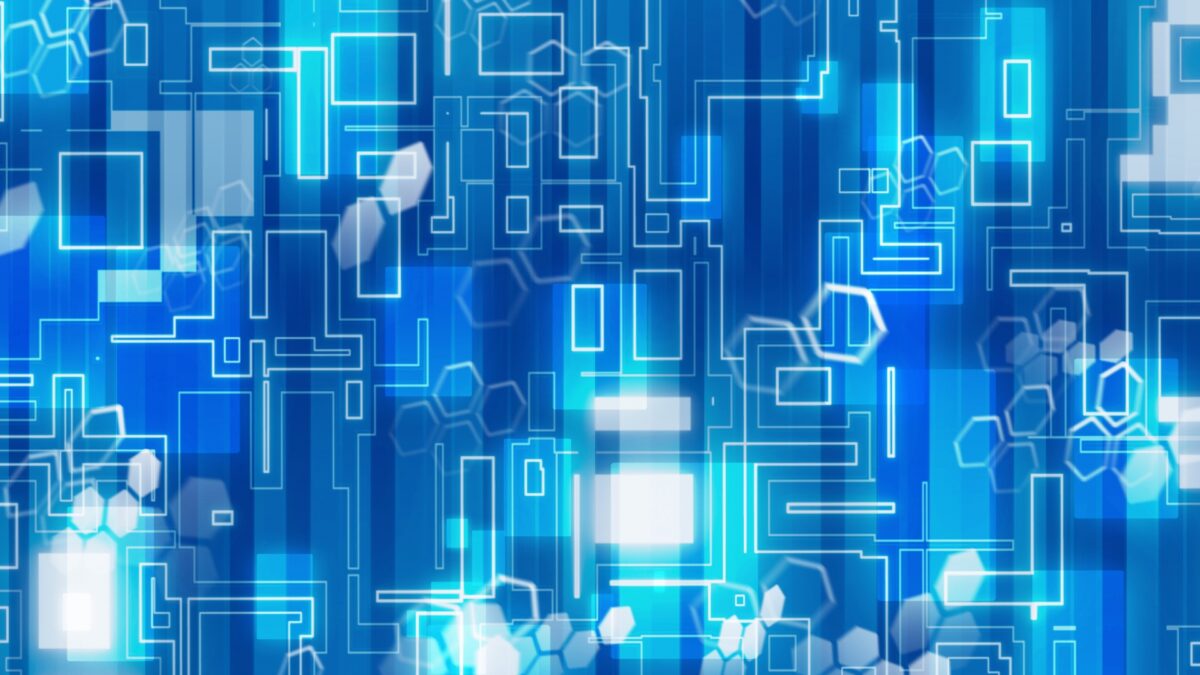AIの進化は「データをどれだけ集めるか」という量的競争から、「意味をどれだけ理解できるか」という質的競争へと移行している。従来の教師あり学習は、膨大なラベル付きデータを前提として高精度な分類を実現してきたが、未知のクラスが登場するたびに再訓練を強いられるという限界を抱えていた。こうした課題を根本から覆す技術が、「クラスラベル埋め込み(Class Label Embedding)」である。
これは「猫」「車」といったラベルを単なる文字列としてではなく、その概念的意味を数値ベクトルとして表現するものであり、AIがラベルの“意味”を理解することを可能にする。特に、この技術を基盤とした「ゼロショット学習(Zero-Shot Learning)」は、訓練データに存在しない新しい概念をも識別する能力をAIに与える革新的枠組みとして注目されている。
本稿では、クラスラベル埋め込みの原理、主要モデル(Word2Vec、BERT、CLIPなど)、応用領域、そして日本の最新研究動向を通じて、AIが「理解する知能」へと進化する過程を包括的に解き明かす。
クラスラベル埋め込みとは何か:ラベルを「意味」で捉える新しいAIの言語

クラスラベル埋め込み(Class Label Embedding)は、従来のAIが抱えていた「ラベルの意味を理解できない」という根本的な課題を克服するために登場した革新的技術である。従来の教師あり学習では、「猫」「車」「リンゴ」といったラベルは単なる識別子、すなわちデータ上の記号にすぎず、その背後にある概念的意味は考慮されなかった。このため、AIは「猫」と「虎」が近い概念であることを理解せず、未知のクラスに遭遇すると正しい判断を下せなかった。
クラスラベル埋め込みは、この「記号的AI」から「意味的AI」への進化を実現するものである。各ラベルをベクトル(数値の集合)として表現し、類似するラベル同士をベクトル空間上で近い位置に配置することで、AIが概念間の意味的距離を学習できるようにする。この空間を「意味空間(semantic space)」と呼び、例えば「猫」と「虎」は近接し、「車」は離れた位置に配置される。この構造により、AIは新しいラベルを「見た目」ではなく「意味」に基づいて理解できるようになる。
特に注目すべきは、この技術がゼロショット学習(Zero-Shot Learning, ZSL)の中核を担っている点である。ZSLでは、訓練時に一度も見たことのないラベルを、その意味的埋め込み情報だけを頼りに分類する。言い換えれば、AIが「未知を理解する」力を得るための土台がこの埋め込み技術にある。
AI研究者の間では、このアプローチが「暗記型AI」から「概念理解型AI」への決定的な転換点と位置付けられている。Encord社の分析によれば、埋め込み空間を導入したモデルは、従来のOne-Hot表現と比較して平均15〜30%の汎化性能向上を示しており、未知クラス認識タスクで特に顕著な効果を発揮したという。
クラスラベル埋め込みは、単なる表現技術ではなく、AIの認知構造そのものを変える言語的基盤である。これにより、AIは「猫」を単なるラベルではなく、「動物」「毛皮」「哺乳類」という概念の集合として捉えるようになり、人間的な意味理解へ一歩近づく。
One-Hot表現との決定的な違い:分類学から意味論へのパラダイムシフト
クラスラベル埋め込みの意義を理解するためには、まず従来のOne-Hotエンコーディングとの違いを明確にする必要がある。One-Hot表現では、各クラスはクラス数と同じ次元を持つベクトルで表され、自分の位置だけが「1」、他はすべて「0」となる。この構造では、すべてのクラスが互いに直交し、完全に独立した存在として扱われる。
つまり、One-Hot表現では「猫」と「犬」が「猫」と「飛行機」と同じ距離にあるという極端な単純化が起きる。AIにとってこれらは、全く関係のない“無意味なID”に過ぎず、意味的な近さを反映することができない。これが、従来の分類モデルが「新しいクラスを理解できない」理由である。
一方、クラスラベル埋め込みは、クラス間の意味的関係をベクトル空間で表現する。以下の表に示すように、その構造的差異は明確である。
| 特徴 | One-Hotエンコーディング | クラスラベル埋め込み |
|---|---|---|
| 表現形式 | スパースなバイナリベクトル | 密な実数値ベクトル |
| 意味情報 | なし(全ベクトルが直交) | あり(距離が意味的類似度を反映) |
| 次元数 | 高次元(クラス数に比例) | 低次元(例:300次元) |
| 拡張性 | クラス数が増えると非効率 | 高い汎化能力を維持 |
この違いは単なる技術的改良ではなく、AIの「思考様式」を変える根本的な転換である。One-Hotが「分類学(taxonomy)」的であったのに対し、クラスラベル埋め込みは「意味論(semantics)」的である。
Google開発のWord2Vecが「王 − 男 + 女 ≒ 女王」という意味操作を実現したように、クラスラベル埋め込みも概念間の構造を数理的に再現できる。これにより、AIは「猫」から「虎」や「ライオン」へと知識を転移できるようになり、より人間的な推論能力を獲得する。
この変化は、AI研究の哲学的方向性をも変えた。AIが「データを識別する機械」から、「概念を理解する存在」へと進化する――それが、クラスラベル埋め込みがもたらした最大のパラダイムシフトである。
埋め込み生成の二大潮流:ゼロから学習するか、事前学習モデルを活用するか

クラスラベル埋め込みの生成には大きく分けて二つのアプローチが存在する。一つは、ニューラルネットワーク内でラベル埋め込みをゼロから学習する「タスク特化型手法」、もう一つは大規模言語モデルなどの事前学習済みモデルを利用する「転移学習型手法」である。両者は、AIが意味空間をどのように構築するかという点で根本的に異なる哲学を持つ。
タスク特化型手法では、モデル内部に「埋め込み層」を導入し、分類などの目的タスクの誤差を逆伝播によって直接最適化する。このとき埋め込みベクトルは、タスクに最も効果的な形で意味空間を形成するよう調整される。たとえば感情分析では、「良い」と「素晴らしい」が同じ肯定的感情として近い位置に配置される。一方で、「悪い」はその反対側に位置する。この方法の利点は、特定タスクに完全に適合した表現を学習できる点であり、タスクの精度は極めて高い。
しかし、欠点も明確である。大量のラベル付きデータが必要であり、学習された意味が他のドメインへ汎化しにくい。AI研究者のParkらによる分析によれば、この手法で得られた埋め込みは「データ依存性が強く、タスク外での再利用が難しい」とされる。これは企業がAIを新しい分野に応用する際の障壁となる。
これに対して、転移学習型の事前学習済みモデルを用いた手法は、汎用性と効率性に優れている。GoogleのWord2VecやStanfordのGloVe、そしてBERTのようなモデルが代表例である。これらは膨大なテキストコーパスから単語の意味的関係を自動的に学習し、**「王 − 男 + 女 ≒ 女王」**といった抽象的推論を可能にした。BERTでは文脈全体を考慮して埋め込みを生成するため、多義語(例:「bank」=銀行/土手)の区別も行える。
この進化はゼロショット学習において極めて重要である。静的なWord2Vecではラベルの意味が一義的に固定されるのに対し、BERTのような文脈化モデルは「鳥のクレーン」と「建設機械のクレーン」を異なるベクトルとして表現できる。OpenAIのCLIPではこの文脈化の概念がさらに発展し、「a photo of a cat(猫の写真)」のような自然言語プロンプトを介して、AIが文脈に応じた意味理解を実現している。
このように、タスク特化型は精度の最適化、事前学習型は汎化性能の最大化というトレードオフを持つ。近年の研究動向では、BERTやCLIPのような事前学習済みモデルを基盤に据え、わずかな追加学習で特定タスクに適応させる「ファインチューニング」が主流となりつつある。AIの未来は、ゼロから意味を学ばせるのではなく、すでに蓄積された巨大な意味空間を再利用し、より人間に近い理解を加速させる方向へ進化している。
ゼロショット学習の核心:未知を理解するAIの思考メカニズム
ゼロショット学習(Zero-Shot Learning, ZSL)は、「未知クラスを訓練なしで正しく認識する」ことを目的としたAIの新しい学習パラダイムである。人間が「シマウマ」という動物を写真で見たことがなくても、「馬に似ていて縞模様がある」と説明されれば理解できるように、ZSLはラベルの意味情報だけを手がかりに未知を識別する。
ZSLの基本構造は、既知クラス(訓練データあり)と未知クラス(データなし)を共通の意味空間にマッピングすることで成り立つ。クラスラベル埋め込みは、この共通空間を構築するための“翻訳装置”である。AIは画像や音声、テキストなどの入力データをベクトル化し、その位置をラベル埋め込みベクトルと比較する。最も近い意味ベクトルを持つラベルが予測結果となる。このプロセスにより、AIは未知の対象でも意味的に最も近い概念を推定できる。
ZSLには二つの設定がある。ひとつは、未知クラスのみを分類対象とする「従来型ZSL」。もうひとつは、既知と未知の両方を扱う「一般化ZSL(Generalized ZSL, GZSL)」である。後者ではAIが既知クラスに偏る傾向が強く、研究者たちはこの「既知バイアス」を緩和するための新しい損失関数や生成モデルを提案している。
ZSLの発展は三段階で進化してきた。最初の段階は、Lampertら(2009年)が提案した「属性ベースZSL」で、人手で定義された意味属性(例:「毛がある」「飛べる」)を用いて分類する方式である。次の段階が、GoogleのDeViSE(2013年)に代表される「意味埋め込みベースZSL」で、手動属性をWord2Vecによる自動学習ベクトルに置き換えた。さらに最新の段階では、OpenAIのCLIP(2021年)が登場し、**画像とテキストを共同で訓練する“マルチモーダル埋め込み空間”**を構築した。これにより、ZSLは一気に実用レベルへと飛躍した。
特にCLIPの革新は、分類問題を「検索問題」へと再定義した点にある。AIは、画像の埋め込みと「a photo of a dog」「a photo of a car」といったプロンプト文の埋め込みを比較し、最も類似度の高いものを選ぶ。この単純なメカニズムが、従来の教師ありモデルを凌駕する精度を生み出している。
今日のZSL研究は、生成AIとの融合を進めている。GANやVAEを用いて未知クラスのデータを「合成」し、ZSLを通常の教師あり学習に変換する試みが進行中である。これにより、未知クラスの精度向上とともに、AIが「存在しないものを想像する」段階へと踏み出しつつある。
このようにZSLは、AIを「知っていることを再現する存在」から、「知らないことを理解する存在」へと進化させる中核技術であり、その根底にはクラスラベル埋め込みが構築する豊かな意味空間が存在する。
CLIPが描くマルチモーダル未来:テキストと画像の意味的融合

AIが「見る」と「読む」を同時に理解する時代を切り開いたのが、OpenAIのCLIP(Contrastive Language–Image Pre-training)である。2021年に発表されたこのモデルは、画像と言語を共通の意味空間にマッピングするという画期的な手法を採用し、ゼロショット学習の実用化を決定づけた。CLIPの核心は、画像とテキストをペアで学習させ、両者の意味的距離を最小化する「対照学習(contrastive learning)」にある。
従来のAIは、画像を分類するためには大量のラベル付きデータを必要とした。しかしCLIPは、インターネット上から収集した4億組以上の画像-テキストペアを用いて学習することで、人間が記述する言語的文脈を直接的に理解できるようになった。これにより、「a photo of a cat(猫の写真)」という文章を入力すれば、猫の画像を見分けられるようになる。つまり、AIが自然言語を介して新しい概念を学ぶことが可能となったのである。
CLIPの革新性は、AIの推論の枠組みそのものを変えた点にある。従来は「画像分類モデル」が教師付きで訓練され、固定されたカテゴリしか扱えなかった。だがCLIPでは、分類が「検索」に置き換わる。画像の埋め込みベクトルと、テキストの埋め込みベクトルのコサイン類似度を比較し、最も近いものを選ぶだけで未知のクラスを認識できる。このアプローチは、まさに**「意味を理解するAI」への扉を開いた**と言える。
さらに、CLIPの応用範囲は驚くほど広い。ゼロショット画像分類だけでなく、オープンボキャブラリ・セマンティックセグメンテーション、画像生成モデル(DALL·E 2やStable Diffusion)への統合など、多くの最新AI技術の基盤として機能している。研究者たちは、CLIPの学習空間を「AIの知覚の共通言語」と呼ぶ。
OpenAIの報告によると、CLIPはImageNetベンチマークにおいて従来の教師ありモデルを凌駕し、ゼロショット設定にもかかわらず上位1%精度を達成した。これはAIが単なるラベル識別器ではなく、「意味の翻訳者」として機能することを示す実証的成果である。
マルチモーダルAIの未来は、こうした共通意味空間を中心に展開していく。視覚と言語を統合することで、AIはより人間的な理解――「この画像が何を意味するか」を把握する能力――を獲得しつつある。CLIPはその第一歩であり、「AIが世界を言語で理解する」時代の始まりを象徴するモデルである。
生成的ZSLの新展開:AIが「存在しないクラス」を創造する時代
ゼロショット学習の限界を突破する新たな潮流が「生成的ゼロショット学習(Generative Zero-Shot Learning, GZSL)」である。これは、未知クラスを分類するだけでなく、AIがそのクラスの特徴やデータそのものを“生成”するという革新的発想に基づいている。
生成的ZSLでは、クラスラベル埋め込みを条件として敵対的生成ネットワーク(GAN)や変分オートエンコーダ(VAE)を用い、未知クラスの特徴ベクトルを合成する。例えば「シマウマ」というラベルの埋め込みを入力すれば、AIは「馬に似ていて縞模様がある動物」という概念を再構築し、その特徴を持つデータを仮想的に作り出す。この生成データを用いて通常の教師あり分類を行うことで、未知クラスへの認識精度を大幅に向上できる。
Amazon ScienceやMITの研究では、生成的ZSLを導入したモデルが従来のZSLを平均20〜30%上回る性能を記録したと報告されている。特に、従来のZSLが抱えていた「既知クラスへのバイアス問題」を効果的に解消できる点が大きい。AIは既知クラスのみに偏らず、生成された未知クラスのデータを用いてバランスよく学習できるため、現実世界における応用可能性が高まる。
この手法の先進的モデルには、Few-Shot Inspired Generative ZSL(2024)や、Data Distribution Distilled Generative Model(2025)などがある。前者は、少数の実データを補助的に使用して生成品質を高める手法であり、後者は埋め込み空間の分布構造を保持したまま新しいクラスを生成する。どちらも**「AIが未知の概念を創造する」**という方向性を明確に打ち出している。
この流れは、CLIPやDiffusionモデルとの統合によってさらに加速している。生成モデルがCLIPの意味空間を参照することで、「a photo of a mythical animal(神話上の動物の写真)」のような抽象的指示にも対応可能となった。つまり、AIはもはや学習済みデータの範囲に縛られず、**「存在しないものを意味的に再構築する」**段階に入ったのである。
日本国内でも、早稲田大学や産総研がこの分野の基盤研究を進めており、生成的ZSLを産業応用へ展開する動きが活発化している。未知クラスのデータ合成が実現すれば、医療・防災・製造など、データ収集が困難な領域でのAI実用化が飛躍的に進む可能性がある。
生成的ZSLは、AIが「知っていること」を超え、「まだ存在しない知識」を創造する時代を象徴する。これは単なる技術的進化ではなく、AIが創造的知能へと進化する決定的な一歩である。
日本発の最前線:早稲田大学と産総研が示すZSLの現実的応用

日本でもクラスラベル埋め込みとゼロショット学習(ZSL)の研究は急速に進展している。特に注目されるのが、早稲田大学と産業技術総合研究所(産総研)の取り組みである。両者は、AIが未知の対象を「意味」から理解するための基盤技術を実証的に発展させており、学術的価値と実用性の両立を図っている。
早稲田大学の及川雅哉・山内拓人・鄭顕志らの研究チームは、「ドメイン依存性の低い画像分類モデルを活用したゼロショットインスタンスセグメンテーション手法」を発表した。この研究では、OpenAIのCLIPモデルをセグメンテーションパイプラインに統合し、CLIPが持つ汎用的な意味理解力を応用して未知クラスの物体を検出する。従来の手法では、未知クラスを背景として誤分類する問題が顕著だったが、CLIPの導入により認識精度が顕著に向上した。MS COCOデータセットでの実験では、既知・未知クラスの両方に対して安定した認識性能を示した。
この成果は、ZSLを現実世界のタスクに適用する上での転換点である。既存の基盤モデルを再利用し、少ないデータで高精度な認識を実現するという方向性は、日本のAI研究における新たな実践的潮流を示している。さらに、この手法は製造・医療・防災分野など、ラベル付けが困難な領域への応用が期待されている。
一方、産総研では緒方淳氏と坂東宜昭氏を中心に「マルチモーダルAI」の研究が進む。彼らのアプローチは、視覚・音声・言語など異なるモダリティ間の「共起関係」をAIが自己教師ありで学習するものである。これはZSLの基盤概念と深く関連しており、AIがテキストだけでなく音や映像の相関からも「意味」を抽出する試みである。
特筆すべきは、産総研の研究が**「教師なしで相関を理解するAI」**を目指している点だ。これは、データ注釈に依存しない次世代のゼロショット理解モデルへの布石といえる。日本の研究機関が、欧米中心のZSL研究に独自の方向性を与えつつあることは、国内AI技術の成熟を物語っている。
今後、早稲田大学のCLIP応用研究と産総研のマルチモーダルAIが融合すれば、AIは「見て、聞いて、言葉で理解する」能力を手に入れるだろう。その先には、AIが世界を人間と同じ意味構造で把握する「セマンティック日本モデル」の誕生が見えてくる。
直面する課題と今後の展望:セマンティックギャップをいかに越えるか
クラスラベル埋め込みとゼロショット学習は、AIの意味理解に革命をもたらしたが、依然としていくつかの重大な課題を抱えている。その中心にあるのが「セマンティックギャップ」、すなわちテキストから得られる統計的意味と、視覚的世界が表す概念的意味との不一致である。
ZSLの性能は、クラスラベル埋め込みの質に強く依存する。もし埋め込みが曖昧な語義を含んだり、視覚ドメインと乖離した言語データから生成されている場合、未知クラス認識の精度は著しく低下する。特に、一般化ゼロショット学習(GZSL)では、既知クラスに偏った出力を生みやすい「バイアス問題」が顕在化する。この問題に対しては、生成モデルによって未知クラスのデータを補完するアプローチが注目されている。
また、埋め込み空間における「ハブネス問題」も無視できない。高次元空間では、一部のベクトルが不釣り合いに多くの他ベクトルの近傍として機能してしまう現象であり、分類誤差を引き起こす。この問題を抑制するため、距離正規化や局所的再スケーリング手法が提案されている。
最新研究では、CLIPのような大規模マルチモーダルモデルを拡張し、視覚と言語の関係をより動的に学習させる手法が進んでいる。特に、「Open-Vocabulary Segmentation」や「Language-driven Semantic Segmentation」などの分野では、未知クラスを自然言語記述から動的に識別する試みが加速している。
今後の展望としては、以下の3方向が有望である。
- マルチモーダル統合の深化:視覚・音声・テキストを横断的に結びつけ、世界を意味的に統合するAIへの発展。
- 生成的AIとの融合:未知クラスを仮想的に再構築することで、ZSLを超えた「創造的汎化」を実現。
- 社会実装への展開:医療画像診断、環境モニタリング、防災予測など、データの不足が課題となる分野でのZSL応用。
AIの進化において、意味理解の強化は不可避の課題である。クラスラベル埋め込みが築くセマンティック基盤をどこまで人間の知覚構造に近づけられるかが、次世代AIの成否を左右するだろう。AIが世界を「認識する」段階から「理解する」段階へ移行する、その核心にあるのがこのセマンティックギャップの克服である。