ここ数年でAI画像認識は驚くほど進化しましたが、「結局、何がどう変わったのか分かりにくい」と感じている方も多いのではないでしょうか。単なる画像分類や物体検知の延長だと思っていると、2026年の現状とのギャップに驚かされるはずです。
現在のAI画像認識は、2次元の画面の中にとどまらず、3次元空間を理解し、物理世界で行動する段階へと進んでいます。製造業の外観検査、医療の画像診断、さらには家庭用ロボットまで、実際の現場で成果を出す「実用技術」として社会に深く入り込んでいます。
本記事では、空間知能や大規模マルチモーダルモデル、Physical AIといった最新キーワードを軸に、技術的ブレークスルーと日本における具体的な導入事例、市場規模や制度面の動きまでを整理します。AIに関心のある方が、今後のトレンドを立体的に理解し、自分の仕事や学習にどう活かせるのかを考えるための視点を提供します。
2026年に起きているAI画像認識のパラダイムシフト
2026年に起きているAI画像認識の最大の変化は、「画像を当てる技術」から「世界を理解する知能」への転換です。かつて主流だった画像分類や物体検知は、ピクセルの集合からラベルを推定する2次元的な処理にとどまっていました。しかし現在は、画像を通じて三次元空間の構造や物体同士の関係、さらには物理的な制約までを推論する段階に入っています。
この転換は、学術界ではAIが「第5の科学的パラダイム」へ進化している流れと重なります。文部科学省のAI for Scienceに関する整理によれば、AIは単なる解析ツールではなく、理論・データ・計算を横断して知識創出を担う基盤になりつつあります。視覚分野では、大規模マルチモーダルモデルの成熟により、画像は単独で解釈される存在ではなく、言語や論理と結び付けて理解される情報源へと格上げされました。
この変化を象徴するのが、空間知能という概念です。AIは写真の中に「何が写っているか」だけでなく、「それが空間のどこに、どのような形で存在し、どう動き得るか」を推定します。CVPRなど主要国際会議でも、画像認識と3D再構成、幾何推論の融合が中心テーマとなり、コンピュータビジョンとコンピュータグラフィックスの境界は急速に薄れています。
| 観点 | 従来の画像認識 | 2026年型の画像認識 |
|---|---|---|
| 理解の次元 | 2次元画像 | 3次元空間 |
| 主な役割 | 識別・検出 | 構造理解・推論 |
| 活用領域 | デジタル内完結 | 物理世界へ拡張 |
特に注目すべきは、3D Gaussian Splattingの普及です。Neural Radiance Fieldsが抱えていたリアルタイム性の課題を克服し、1080p解像度で200FPSを超える描画性能を実現しました。MDPIのサーベイ論文でも指摘されている通り、この手法は幾何学的再現性と実時間処理を両立させ、都市空間の再現やインフラ点検など、実用的な画像認識の前提条件を大きく引き上げています。
さらに、CVPR 2025で最優秀論文賞を受賞したVisual Geometry Grounded Transformerは、視覚モデルに幾何学的制約を組み込むことで、複数視点から空間構造を直接推定できることを示しました。これは、AIが経験的に見た目を学ぶ段階から、数学的整合性を保ちながら空間を理解する段階へ進んだことを意味します。
このパラダイムシフトの本質は、画像認識が「補助的な判断材料」から「意思決定の基盤」へ変わった点にあります。製造、医療、ロボティクスといった現場では、AIが見たものを前提に行動や判断が組み立てられます。2026年のAI画像認識は、もはや視覚の自動化ではなく、人間社会の認知構造そのものを再設計する技術段階に入っています。
2次元から3次元へ進化する空間知能のインパクト
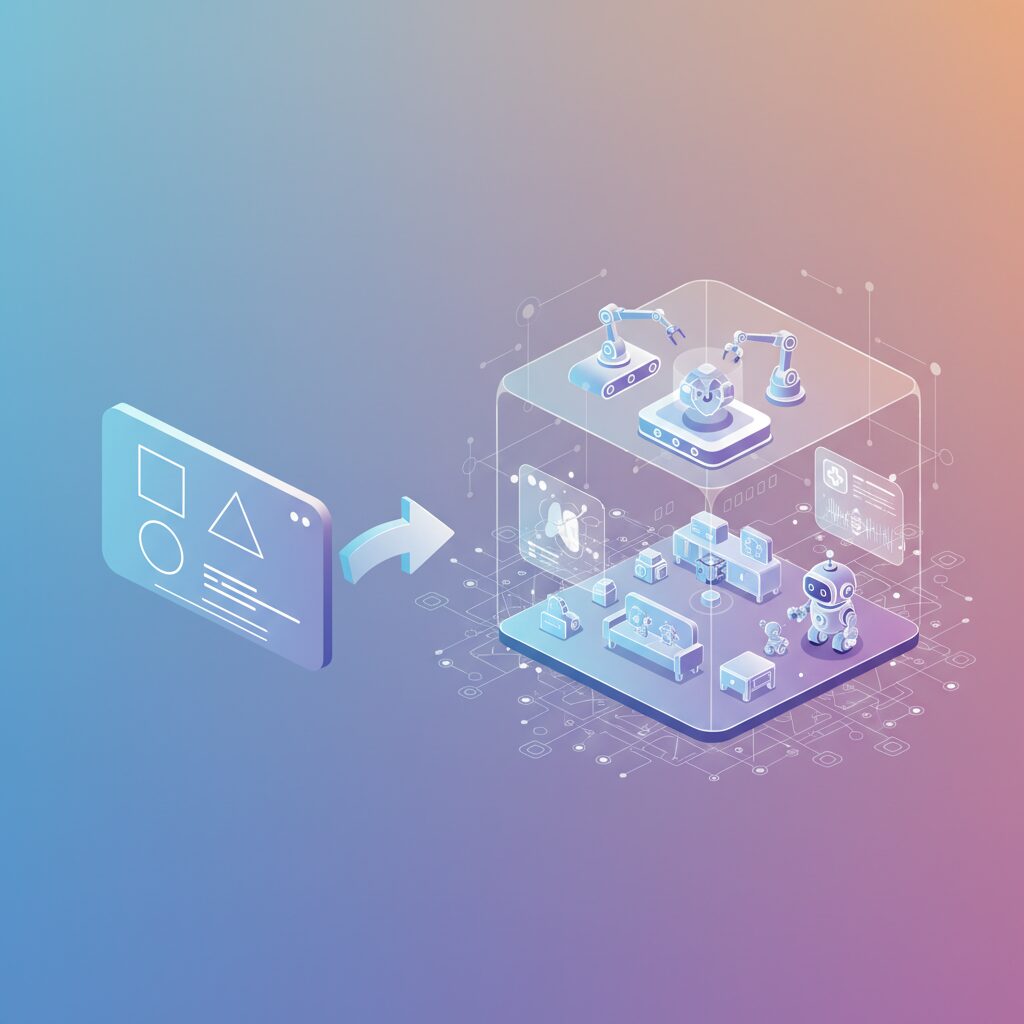
2次元の画像認識から3次元の空間知能への進化は、AIが「見る」存在から「空間を理解し、振る舞いを予測する」存在へと変わったことを意味します。従来のAIは平面上のピクセル配置から物体を分類・検出することが中心でしたが、2026年現在では、カメラ映像から奥行きや形状、位置関係を推定し、現実空間そのものをモデル化できる段階に入っています。
この転換点を象徴する技術が、3D Gaussian Splatting(3DGS)です。Neural Radiance Fieldsが切り拓いた3D再構成の概念を、実用レベルの速度へと引き上げ、フルHD環境で200FPS超のリアルタイム描画を可能にしました。これにより、3D空間理解は研究用途から産業インフラへと一気に近づいたのです。
実際、MDPIに掲載された複数のサーベイ論文によれば、3DGSは都市スケールの環境再現や複雑な構造物のデジタル化において、従来手法よりも境界表現の精度が高いと評価されています。これは、スマートシティ設計やインフラ点検、文化財保存といった分野での活用を現実的なものにしました。
| 観点 | 2次元画像認識 | 3次元空間知能 |
|---|---|---|
| 理解対象 | 平面上の特徴 | 奥行き・形状・位置関係 |
| 推論能力 | 静的な分類・検出 | 空間的因果関係の推定 |
| 主な応用 | 画像検索、検品 | 自動運転、ロボティクス、AR |
さらに、CVPR 2025で最優秀論文に選ばれたVGGTは、複数視点の画像から幾何構造を直接推定することで、3D理解をリアルタイム処理の領域へ押し上げました。学会関係者の間では、これは「何が写っているか」から「それがどこにどう存在するか」への決定的な飛躍だと評されています。
この空間知能の最大のインパクトは、AIが物理世界と直接結びついた点にあります。ロボットや自動運転車は、単なる視覚センサーではなく、行動判断の基盤として3D世界モデルを利用するようになりました。結果として、AIは画面の中の分析ツールから、現実空間で価値を生み出す主体へと進化しつつあります。
2次元から3次元への移行は、精度向上にとどまらず、AIの役割そのものを再定義しました。空間を理解できるAIは、次の瞬間に何が起こり得るかを推論できるため、人間の判断を補助するだけでなく、代替する領域を急速に広げています。この変化こそが、空間知能が社会に与える本質的なインパクトです。
3D Gaussian Splattingが実用標準になった理由
3D Gaussian Splattingが実用標準として定着した最大の理由は、研究室レベルの技術を産業現場へと一気に引き下ろした圧倒的な実行性能にあります。Neural Radiance Fieldsが提示した高精細な3D再構成という理想は魅力的でしたが、1フレームの描画に数秒から数分を要する計算負荷は、リアルタイム性が必須な現場では致命的でした。そのボトルネックを、3DGSは根本から解消しました。
3DGSは空間を連続関数としてではなく、数百万個のガウス楕円体の集合として表現します。この発想の転換により、レンダリングはニューラルネットワーク推論ではなくGPUの得意とするラスタライゼーションに帰着されます。MDPIのサーベイ論文でも指摘されている通り、1080p解像度で200FPSを超える性能は、AR、ロボティクス、デジタルツインといった分野で「使える」水準を初めて満たしました。
| 観点 | NeRF | 3D Gaussian Splatting |
|---|---|---|
| レンダリング速度 | 数秒〜数分/フレーム | 100FPS以上 |
| 表現の単位 | 連続関数(MLP) | ガウス楕円体 |
| 編集・操作性 | 再学習が必要 | 局所的な編集が可能 |
実用標準になったもう一つの決定的要因は、編集性と運用性の高さです。NeRFではモデル全体が暗黙的に空間を保持するため、一部を修正するだけでも再学習が必要でした。一方3DGSでは、楕円体という明示的な構成要素を直接操作できます。これにより、点群編集に近い感覚での修正や、不要部分の削除が可能となり、制作フローに人間が介在できる余地が生まれました。
この「人が扱える3D表現」であることが、産業導入を一気に加速させました。文化財のデジタル保存では、研究者が意図的に欠損部を補正し、インフラ点検では必要箇所のみを高密度化するといった運用が現実的になっています。Chang’an Universityの研究グループが提案した深度情報を統合する手法も、既存モデルを拡張する形で適用でき、実装コストを抑えた高度化を実現しました。
さらに重要なのは、3DGSが単体技術としてではなく、エコシステムの中心に据えられた点です。CVPRやICCVの主要セッションでは、3DGSを前提とした深度正則化、動的シーン対応、エッジデバイス実装が相次いで発表されました。Paper Digestの分析によれば、2025年以降の3D再構成研究の多くが3DGSをベースラインに採用しています。
結果として3D Gaussian Splattingは、「最も美しい3D表現」ではなく、「最も現実に耐える3D表現」として評価されました。速度、編集性、拡張性という三点を同時に満たしたことが、2026年時点での実用標準という地位を揺るぎないものにしています。
幾何学的理解を組み込んだ次世代トランスフォーマー

幾何学的理解を組み込んだ次世代トランスフォーマーは、従来の画像認識モデルとは根本的に異なる発想から生まれています。これまでのトランスフォーマーは、画像をトークン化し、その相関関係を統計的に捉えることで高い認識精度を実現してきました。しかしこの手法では、空間そのものの構造や物理的な制約を内在化することが難しく、3次元理解には限界がありました。
この壁を突破した代表例が、CVPR 2025で最優秀論文賞を受賞したVisual Geometry Grounded Transformer(VGGT)です。VGGTは複数視点の画像を入力とし、注意機構そのものに幾何学的制約を組み込むことで、シーンの形状や位置関係を直接推定します。**「何が写っているか」ではなく、「それが空間のどこに、どのような構造で存在するか」を同時に理解できる点**が、従来モデルとの決定的な違いです。
| 観点 | 従来型トランスフォーマー | 幾何学的トランスフォーマー |
|---|---|---|
| 主な学習対象 | 意味的相関 | 意味+空間幾何 |
| 3D理解 | 間接的 | 直接推定 |
| 制約条件 | データ依存 | 数理的制約を内包 |
VGGTの技術的インパクトは、推論速度にも表れています。フィードフォワード型の構成により、数百視点の画像を統合しながらもリアルタイム処理が可能であり、自動運転やロボティクスのような即時判断が求められる領域で高く評価されています。CVPRの公式レポートによれば、このアプローチは従来のSfMやSLAM系パイプラインを置き換える可能性があると指摘されています。
さらに重要なのは、幾何学的トランスフォーマーが「学習の安定性」を飛躍的に高めている点です。物理的にあり得ない形状や位置関係を、モデル構造レベルで排除できるため、視覚的ハルシネーションの抑制にも寄与します。**これは精度向上だけでなく、AIを社会インフラとして利用する上で不可欠な信頼性の基盤**となります。
研究コミュニティでは、VGGTを起点として、3D Gaussian Splattingや深度推定モデルと統合する動きも加速しています。幾何学的に整合した3D表現をトランスフォーマーが理解し、推論結果をそのまま現実空間の操作に結び付ける。この流れは、視覚知能が「認識」から「空間的意思決定」へ進化したことを象徴しています。
幾何学的理解を組み込んだ次世代トランスフォーマーは、単なるモデル改良ではありません。数学、物理、視覚を統合することで、AIが世界を構造として捉え始めた転換点であり、2026年以降の空間知能の中核技術として位置づけられています。
画像認識と大規模言語モデルの融合がもたらした変化
画像認識と大規模言語モデルの融合は、AIの役割を「見る機械」から「理解し、説明し、判断する存在」へと押し上げました。2026年現在、この変化は単なる精度向上ではなく、人間とAIの関係性そのものを変える質的転換として捉えられています。
従来の画像認識は、物体検知や分類といったタスク単位の最適化が中心でした。しかし大規模マルチモーダルモデルの成熟により、画像は言語的推論の入力として扱われ、**画像の内容を文脈・因果・意図のレベルで解釈する**ことが可能になっています。文部科学省のAI for Science関連資料によれば、視覚情報と言語推論の統合は、科学的発見の自動化を加速させる基盤技術と位置づけられています。
この融合の象徴的な例が、DeepSeek-VL2のような最新MLLMです。画像、図表、数式、長文テキストを同一の推論空間で扱い、最大129Kトークンの文脈を保持したまま解釈できます。これにより、研究論文の図表解読や、企業の膨大な技術資料からの知識抽出が実用段階に入りました。
| 観点 | 従来の画像認識 | 画像×LLM融合後 |
|---|---|---|
| 処理対象 | 単一画像・短文 | 画像+長文文脈 |
| 理解の深さ | 特徴量レベル | 意味・因果レベル |
| 出力 | ラベル・座標 | 自然言語による説明 |
さらに重要なのが、視覚的ハルシネーションへの対処です。EMNLP 2025で報告されたSPINや、RCDといった新しいデコーディング戦略により、**画像と矛盾する説明を生成する確率が大幅に低減**しました。ACL Anthology掲載論文によれば、特定のアテンションヘッドを制御するだけで、精度とスループットを同時に改善できることが示されています。
この結果、医療画像診断や製造業の検査レポートなど、説明責任が求められる領域での活用が急速に広がりました。AIが「なぜそう判断したのか」を言語で説明できるようになったことは、単なる自動化を超え、現場の意思決定を支える知的パートナーへの進化を意味しています。
画像認識と大規模言語モデルの融合は、視覚情報を社会で使える知識へと変換する翻訳装置をAIに与えました。この変化こそが、2026年以降のAI実装を支える最も本質的な基盤となっています。
視覚的ハルシネーション対策技術の現在地
視覚的ハルシネーション対策は、2026年時点で「付加的な安全機能」から「マルチモーダルAIの中核技術」へと位置づけが変わっています。画像の内容と矛盾する説明文を生成してしまう問題は、医療や製造、法務といった高信頼性が求められる現場では致命的であり、研究と実装の両面で急速な進展が見られます。
近年の重要なブレークスルーは、ハルシネーションを単なる生成ミスではなく、モデル内部の注意機構に起因する構造的問題として捉えた点にあります。OpenReviewやACL Anthologyに掲載された複数の研究によれば、誤った視覚記述は特定のアテンション・ヘッドが画像情報を十分に参照せず、言語的な補完に走ることで発生しやすいと分析されています。
この知見を実装に落とし込んだ代表例が、EMNLP 2025で発表されたSPINです。SPINは推論時に画像トークンへの寄与が低いヘッドを選択的に抑制し、**追加学習なしでハルシネーションスコアを最大2.7倍改善**したと報告されています。しかも計算負荷は増えず、スループットが約1.8倍向上する点は、商用サービスにおいて極めて現実的です。
| 技術名 | 主な仕組み | 確認された効果 |
|---|---|---|
| SPIN | 低寄与アテンション・ヘッドの抑制 | ハルシネーション大幅低減、推論高速化 |
| RCD | 類似画像との対照的デコーディング | 学習不要で視覚的一貫性を向上 |
もう一つの潮流がRCDです。これは「似た画像は似た誤りを生む」という現象を逆手に取り、外部から取得した類似画像と生成候補を比較しながらデコードする手法です。LLaVA-NextやInstructBLIPなど複数のモデルで既存手法を上回る精度が示されており、**モデルを改変せずに導入できる点**が企業利用を後押ししています。
さらに2025年以降、ハルシネーションを完全排除すべき欠陥とみなす考え方自体が見直されています。Lakeraなどの専門家は、生成結果に対する自己確信度を適切に調整し、不確実な場合は「分からない」と返すキャリブレーションこそが重要だと指摘しています。これは、人間の専門家が断定を避ける態度に近づける試みと言えます。
この流れにより、マルチモーダルAIは万能な説明装置ではなく、根拠と限界を併せ持つ知的パートナーとして再定義されつつあります。視覚的ハルシネーション対策の成熟度は、今後のAI導入可否を判断する重要な指標になっていくでしょう。
生成AIと画像認識が一体化する新しいワークフロー
生成AIと画像認識が一体化することで、AI活用のワークフローは「人が指示し、AIが部分的に処理する」段階から、「AI自身が見て考え、次の行動を組み立てる」段階へと進化しています。2026年時点では、大規模マルチモーダルモデルの成熟により、画像入力が単なる補助情報ではなく、意思決定の起点として扱われるようになっています。
例えば、現場の写真やスクリーンショットをAIに渡すだけで、状況把握、課題抽出、対応案の生成までが一連で行われるケースが増えています。これは画像認識モデルが視覚的特徴を抽出し、生成AIがその意味や因果関係を言語化・構造化することで成立しています。NatureやCVPR関連論文でも、視覚情報と言語推論を統合したモデルがタスク成功率を大幅に高めることが示されています。
| 従来のワークフロー | 統合後のワークフロー |
|---|---|
| 画像は人が解釈 | 画像をAIが直接理解 |
| テキスト指示が中心 | 視覚入力が起点 |
| 工程ごとにツール分断 | 単一モデルで連続処理 |
この変化が特に顕著なのが、業務オペレーションとクリエイティブ制作の分野です。製造現場では、設備写真を読み込んだAIが異常箇所を指摘し、そのまま改善手順書のドラフトを生成します。広告やECでは、商品画像を解析した上で、訴求ポイントを抽出し、コピー案やバナー構成まで自動生成される流れが一般化しつつあります。
重要なのは、画像認識が「答えを出す」役割から、「思考の材料を供給する」役割へと変わった点です。生成AIは画像を見て即断するのではなく、空間構造、配置、文脈を踏まえた上で推論を重ねます。GoTのような推論プロセスを明示的に挟む手法が登場したことで、出力の一貫性と説明可能性も向上しています。
また、視覚的ハルシネーション抑制技術の進展により、画像とテキストの齟齬は大幅に減少しました。EMNLPやOpenReviewで報告されているSPINやRCDといった手法は、実運用においても誤認識率を抑え、ワークフロー全体の信頼性を底上げしています。これにより、AIの出力を人が逐一確認する負担が軽減されています。
結果として、生成AIと画像認識が融合した新しいワークフローは、「入力形式の多様化」ではなく「思考プロセスの自動化」を実現しています。AIに画像を見せる行為そのものが、タスク設計や要件定義を兼ねるようになり、人間はより抽象度の高い判断や創造に集中できる環境が整いつつあります。
Physical AIが切り拓くロボットと実世界応用
Physical AIは、視覚知能が物理的な身体性を獲得し、現実世界で自律的に行動する段階へ進んだことを象徴する概念です。2026年は、AIがスクリーン内の分析役から、実際に手足を動かして価値を生み出す存在へ転換する節目の年と位置づけられています。東京大学の松尾豊教授も、この年をAIが物理空間へ本格進出する歴史的転換点と捉えています。
この潮流を端的に示す事例が、ノルウェーの1X社による家庭用ヒューマノイドNEOです。NEOは単なる画像認識ロボットではなく、周囲の環境を3次元的に把握し、行動結果を予測する世界モデルを内部に構築しています。カメラやセンサーから得られる視覚情報をもとに、家具の配置や人の動線を理解し、障害物を避けながら家事を遂行する能力は、従来の産業ロボットとは質的に異なります。
こうしたロボットの実世界応用を支える重要な要素が、エッジAIです。物理空間ではクラウド往復による遅延が致命的になるため、低消費電力かつ即時応答が不可欠です。QualcommがCVPR 2025で発表したCustomKDは、DINOv2やCLIPといった巨大な視覚基盤モデルの知識を、ロボットやモバイル端末向けの軽量モデルへ蒸留する技術です。これにより、高度な視覚理解をローカル環境で実行できるようになりました。
Physical AIが適用される領域は、家庭だけにとどまりません。倉庫内のピッキング、工場内の柔軟な組立作業、さらには人と同じ空間で働く協働ロボットなど、実世界応用は急速に拡大しています。特に労働力不足が深刻な日本では、視覚認識と行動計画を統合したロボットの社会的インパクトは極めて大きいといえます。
| 応用領域 | Physical AIの役割 | 期待される効果 |
|---|---|---|
| 家庭 | 3D環境理解による家事支援 | 日常作業の自律化、介護負担の軽減 |
| 製造・物流 | 視覚と動作の統合制御 | 人手不足の補完、生産性向上 |
| サービス業 | 人との空間共有と安全な動作 | 新しい接客・業務形態の創出 |
重要なのは、Physical AIが万能な自律存在としてではなく、人間の活動を補完する設計思想で進化している点です。視覚知能が現実世界を正確に理解し、安全かつ説明可能な形で行動することが、社会受容の前提条件になります。研究と産業実装の両面で積み重ねられてきた成果が、2026年に入り、ようやく実世界での実利として結実し始めています。
ロボットが見ることと動くことを同時に学習する時代において、Physical AIはAI進化の到達点ではなく、新たな出発点です。視覚知能が物理世界と深く結びつくことで、これまで自動化が困難だった領域にも、現実的な解が提示され始めています。
日本の製造業・医療分野で進む社会実装の実例
日本の製造業と医療分野では、AI画像認識が「試験導入」の段階を完全に終え、現場の成果として定量的に評価される社会実装フェーズに入っています。背景にあるのは深刻な人手不足ですが、単なる省人化にとどまらず、**品質・安全性・再現性を同時に高めるインフラ技術**として位置づけ直されている点が重要です。
製造業では、外観検査AIが第2世代へと進化しています。従来は不良品画像を大量に学習させる教師あり学習が主流でしたが、近年は「良品のみを学習し、逸脱を異常と判断する」半教師あり学習が定着しました。これにより、現場でほとんど発生しない未知欠陥にも対応できるようになっています。経済産業省関連資料や業界調査によれば、この方式は過検出を大幅に減らし、検査員の再確認工数を削減する効果が確認されています。
| 企業 | 検査対象 | 導入効果 |
|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 生産ライン全般 | 見逃し率の事実上ゼロ化 |
| 日本精工 | 精密ベアリング | 検査精度99.9% |
| 相川プレス工業 | 自動車用部品 | 検査時間を約3分の1に短縮 |
さらに2025年以降は、生成AIを活用して「疑似不良画像」を人工的に作成し、学習データを補完する手法が実用化されています。これにより、熟練検査員の経験知をデータとして継承できるようになりました。**AIが判定理由を自然言語で説明するXAI機能**も現場で評価されており、「なぜ不良と判断したのか」が共有されることで、人とAIの協働関係が成立しています。
医療分野でも社会実装は急速に進んでいます。厚生労働省の薬事承認を受けた画像診断支援AIは、すでに日常診療の一部として組み込まれています。エルピクセル社のEIRLシリーズは、胸部X線や脳MRAなど複数領域で累計640万件以上の解析実績を持ち、800を超える医療機関で利用されています。国内外の臨床研究によれば、**読影医の見落としを補完し、診断のばらつきを抑制する効果**が示されています。
内視鏡領域では、AIメディカルサービスや富士フイルムの製品が、がんのリアルタイム検出を実現しました。これらは医師の判断を置き換えるものではなく、注意喚起を行う「第二の目」として設計されています。専門医不足が深刻な地域医療においても、一定水準の診断品質を担保できる点は大きな社会的意義があります。
製造業では品質の再現性を、医療では診断の公平性を高める技術として、AI画像認識は不可欠な社会基盤になりつつあります。
東京大学病院などでは、短時間の動画から生活習慣病リスクを推定する研究も進んでおり、将来的には予防医療への展開が期待されています。日本の製造業と医療分野に共通するのは、AIをブラックボックスとして扱わず、現場知と結びつけて運用している点です。**この「現場起点の実装力」こそが、日本におけるAI社会実装の最大の競争優位性**と言えるでしょう。
市場規模・国家戦略から見る日本のAI画像認識の未来
日本のAI画像認識の未来を読み解くうえで、市場規模の拡大と国家戦略の方向性は切り離せない視点です。総務省の令和7年版情報通信白書によれば、国内AIシステム市場は2024年に1兆3,412億円に達し、前年比56.5%増という異例の成長を記録しました。この成長曲線は一過性ではなく、2029年には4兆円超へと拡大する見通しが示されています。
特に画像認識を中核とする分野は、製造・医療・インフラといった基幹産業に直結している点で、日本経済への波及効果が大きいと評価されています。単なるIT投資ではなく、労働力不足や品質維持といった構造課題への対応策として導入が進んでいることが、市場の持続的成長を支えています。
数字から見た日本のAI市場動向を整理すると、以下のような特徴が浮かび上がります。
| 項目 | 規模・時期 | 示唆される意味 |
|---|---|---|
| AIシステム市場 | 2024年:1.34兆円 | 社会インフラ化の初期段階 |
| 同市場予測 | 2029年:4.19兆円 | 全産業への本格浸透 |
| AIエージェント市場 | 2030年:3.56兆円 | 自律的視覚AI需要の爆発 |
こうした市場拡大を国家レベルで後押ししているのが、日本政府の明確なAI戦略です。経済産業省が主導するGENIACプロジェクトでは、生成AIだけでなく画像認識を含むマルチモーダルAIの国産化と実装力強化が重点テーマに据えられています。2026年度予算ではAI・半導体分野に1兆円規模の公的資金が投じられ、研究から社会実装までを一気通貫で支援する体制が整えられました。
また、2025年末に閣議決定された人工知能基本計画は、技術振興と同時に信頼性と安全性を制度面から担保する枠組みです。これにより企業は、画像認識AIを現場に導入する際の法的・倫理的リスクを見通しやすくなり、結果として投資判断が加速しています。
市場の急成長、国家戦略による後押し、そして現場ニーズの一致という三条件がそろった現在、日本のAI画像認識は「研究先行型」から「実装主導型」へと明確にフェーズを移しつつあります。この流れは今後、国内だけでなく、信頼性を重視する日本発ソリューションとして国際市場へ広がっていく可能性も秘めています。
参考文献
- Paper Digest:Key Computer Vision Trends: ICCV 2023 vs 2025
- MDPI Sensors:Trends and Techniques in 3D Reconstruction and Rendering: A Survey with Emphasis on Gaussian Splatting
- CVPR:CVPR 2025 Unveils the Latest Trends in Artificial Intelligence
- SiliconFlow:deepseek-vl2 – Model Info, Parameters, Benchmarks
- 総務省:令和7年版 情報通信白書|市場概況
- Qualcomm:AI and computer vision insights at CVPR 2025
